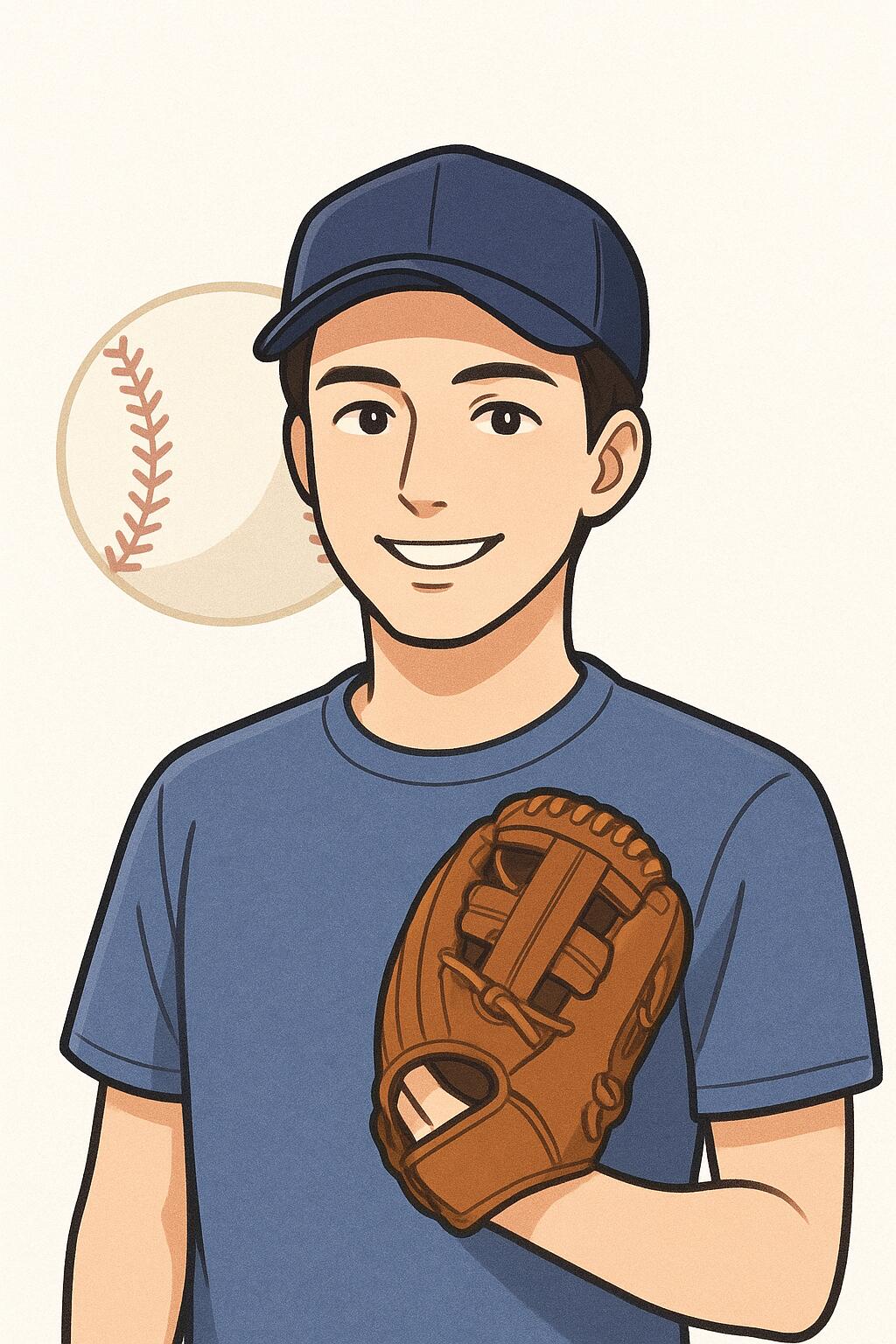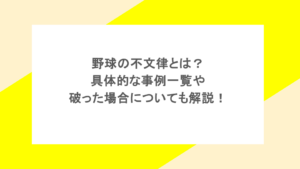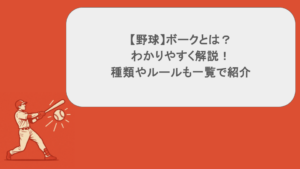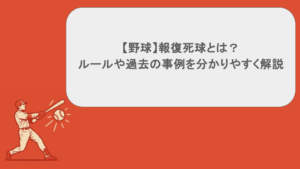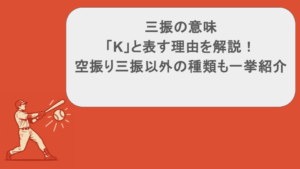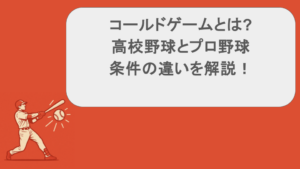野球の解説で時々耳にするタイブレークとは、何を意味しているのでしょうか?もともとあったルールではないので、一体いつからできた?と疑問に思っている人も少なくないようです。
今回は、タイブレークとはどのようなものなのか詳しく解説いたします。高校野球とプロ野球におけるタイブレークの違いも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
タイブレークとは?
タイブレークには、次のルールが設けられています。
- 開始イニングは10回から
- ノーアウトから開始
- ランナーの配置と打順に決まりがある
- 15回を超えても試合続行
- 途中終了になった場合は再試合
10回で決着が付かずに延長戦になった場合、選手の体調に配慮することを目的として作られたのがタイブレークです。それぞれのルールを掘り下げていきましょう。
開始イニングは10回から
タイブレークが導入された2018年は13回から開始でしたが、2023年度からは10回に変更されました。
野球の試合は通常9回まで行われますが、決着が付かない場合は延長になります。ただし、延長になったからといってすぐに勝敗が決まるわけではありません。実際、過去に行われた全国高校野球選手権大会では、最長で25回まで試合が続いた記録も残っています。
ノーアウトから開始
タイブレークはノーアウト1・2塁から開始されます。
早期に決着を付けることを目的としているため、点が入りやすい状況になるということですね。先攻で打席に立つのがホームランバッターだった場合、タイブレーク開始早々に最大で3点が入る可能性もあります。
後攻でも3点が入れば試合は続行しますが、入らなければそこで試合終了です。
ランナーの配置と打順に決まりがある
タイブレークではランナーの配置にも決まりがあります。
1つ前の打順の選手が2塁に付くので、打席に立つバッターが4番だった場合は1塁に3番バッターが立つというのがルールです。ランナーが最初から塁に出ているのは得点チャンスですが、足が速くない選手だった場合は不利ということになります。
ただし、ピッチャーが1つ前の打順の選手だった場合は、さらに前のバッターと交代することも可能です。
15回を超えても試合続行
タイブレークでは、15回で決着が付かなくても試合を続行します。
ただし、1日の登板はピッチャー1人につき15イニングまでと決められているため、試合が長引くほど勝率が下がってしまう点がネックです。とはいえ、1人の選手がずっと投げるのは望ましいことではありません。
肩や肘への負担が大きくケガの原因にもなるため、制限が設けられるのは仕方がないといえるでしょう。
途中終了になった場合は再試合
15回を超えても決着が付くまで試合は続行されますが、やむを得ない理由で続けられない場合は途中終了となります。
近年は異常気象でゲリラ豪雨も多いので、審判が試合を続行させることはできないと判断したときは再試合の可能性もあるでしょう。とはいえ、2025年現在まで15回を超えて再試合になったことはありません。
高校野球に導入されたのはいつから?
高校野球にタイブレークが導入されたのは2018年です。
導入から現在までの流れは以下をご覧ください。
- 2014年:地方大会を含む一部の試合で導入
- 2015年:春季都道府県及び地区ブロック大会で試験的に導入
- 2018年:春の選抜高校野球大会からタイブレーク導入。ただし、決勝戦では採用なし。
- 2021年:春の選抜高校野球大会から決勝戦でもタイブレークを導入
- 2023年:タイブレークの開始イニングが13回から10回へ変更
酷暑が続いているので、今後も変更があるかもしれませんね。
導入前は何回まで延長していた?
タイブレーク導入前の延長は15回までと定められていました。
15回まで進んでも決着が付かず引き分けになった場合は再試合となっていましたが、2017年の選抜高校野球大会では珍事が起きています。2試合連続で引き分け再試合になるという異例の事態を受け、タイブレークの全面導入が検討されました。
2試合連続で延長になったのは後にも先にも2017年の大会だけです。
野球の延長は何回まで?
高校野球では10回からタイブレーク制が適用されるため、決着が付くまで無制限で試合が行われます。一方、プロ野球ではタイブレーク制が導入されていません。延長は12回までと決まりがあり、決着が付かなかった場合は引き分けとなります。
では、MLBではどうなのかというと、延長回数の制限は設けられていません。引き分けという概念がないので、10回から適用されるタイブレークによって試合が続行されます。
高校野球の歴史に残る延長戦
タイブレークが導入された背景には、歴史に残る数々の延長戦の記録がありました。
90年代以降で日本中から注目を集めた延長戦は次の2試合です。
- 1998年:第80回全国高校野球選手権大会にて、横浜高校とPL学園が準々決勝で延長17回
- 2006年:第88回全国高校野球選手権大会にて、早稲田実業高校と駒沢大学附属苫小牧高校が延長15回で再試合
横浜高校では松坂大輔、早稲田実業高校では斎藤佑樹、駒沢大学附属苫小牧高校では田中将大が登板していました。
高校野球にタイブレークはいらない?
高校野球のタイブレーク制には、検討段階から反対の声が多く上がっています。選手の体調への負担を考慮して設けられたルールではありますが、早く決着が付きやすいようになっている分、見応えがないというのも事実です。
せっかく9回まで引き分けへ持ち込んでも10回であっけなく終了してしまうこともあるため、運に左右される部分も否定できません。
プロの中にも高校野球にタイブレークはいらないと考える人は一定数いるようで、長年ヤクルトスワローズで監督をしていた野村克也も反対していました。
まとめ
今回は、タイブレークとはどのようなものなのか、ルールを1つずつ掘り下げて解説いたしました。
タイブレークとは、延長戦になった際にできるだけ早く決着を付けるために設けられたルールです。高校野球では2018年から本格的に導入が開始された一方で、プロ野球では採用されていません。
野球ファンからは「見応えがない」「もったいない」という理由で、タイブレークはいらないのではないかという声が多く上がっています。